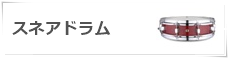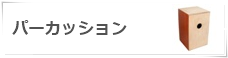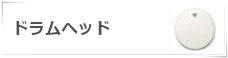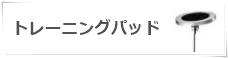メトロノームの使い方&おすすめアプリ
メトロノームを練習に用いることは、ドラムやパーカッションなどの打楽器に限らず楽器演奏における正確なリズム感・タイム感を養うためにも非常に有効です。
ただ、使えばそれで良いわけではなく、計画性なしに漠然とメトロノームを鳴らしながら練習を行っても実はあまり効果が見込めないのです。
それでは、より正確なリズムの感覚を身に付ける効果的なメトロノームの使い方とはどのようなものなのでしょうか。
ここでは
- メトロノームの効果的な使い方
- メトロノームの必要な機能とおすすめアプリ
というテーマで、アドバイスさせていただきたいと思います。
1.メトロノームの効果的な使い方
「クリック依存症」について
突然ですが、「クリック依存症」という言葉を聞いたことはありますか?
これはその名の通り、「メトロノームのクリック音に依存してしまっている症状」のことです。
もっと具体的に言うと「クリック音に合わせて演奏できるが、その音がないとテンポキープができず、走ったり(速くなる)もたれたり(遅くなる)してしまう」ということです。
バンドメンバーに「ドラム、走ってるぞ!」とか、吹奏楽の指揮者に「パーカッション、そこ遅くなる!」などのようにテンポを指摘されることはアンサンブルの練習現場ではよくあることです。。
もちろん、人間なのでメトロノームやリズムマシンなしに、曲初めから終わりまでテンポを1すらぶれることなく演奏することは極めて困難です。
ただし、音楽においてリズムの要であるドラマーやパーカッショニストが、アンサンブルの度にテンポが揺れるようでは、いくらテクニックがあっても使い物になりませんね・・・
機械のように一寸の狂いもなく正確にリズムを刻む必要はないですが、やはり許容範囲というものがあります。
それでは、このような「クリック依存症」に陥ってしまっている人の練習の特徴を挙げてみます。
- そもそも、練習にメトロノームを一切使用しない。
- 練習の終始、ずっとクリック音を鳴らしている。
- 毎回、同じテンポで練習している。
まず、メトロノームを使ったことがないという方には「ぜひ、練習にはメトロノームを使いましょう」と勧めることから始めるのですが、実は上記に挙げたような使用方法ではほとんど効果は見込めない上、クリック音なしではテンポ・キープができない「クリック依存症」に陥ってしまう可能性が高いのです。
インプットとアウトプット
同じテンポのクリック音をずっと鳴らしながらの練習は決して間違いではないですが、これだけでは十分にリズム感を養ったり、テンポキープの向上に繋げることはできません。
なぜなら、クリック音に合わせて叩くというのはビートを感じ取る作業だけにすぎないからです。
この作業を私的には「インプット」と呼びます。
練習でメトロノームを使う大きな目的は、自分の体内に均等なビート(拍子)感を植え付け(インプット)、さらにビート感を自分で創り出すこと(アウトプット)です。
そして、体内リズムを植え付け、創り出すための具体的なメトロノームの使い方はクリック音ありの状態で安定して演奏できるようになった後は、今度はクリック音を消してそのビート(拍子)を意識的に頭で感じながら繰り返し練習することです。
このように、クリック音ビート感を植え付ける作業(インプット)と、創り出す作業(アウトプット)を繰り返すことで体内への定着を図るわけです。
レコーディングでシーケンサーと同期するような場合を除いては、基本的にライブやコンサートでクリック音を鳴らすことはありませんね。
よって、クリック音に合わせることができても最終的に体内リズムを創れなければ効果がないのと同じことです。
練習毎にテンポを変える
また、気を付けなければいけないのは毎回同じテンポで練習しないことです。
テンポの癖がついてしまい、その前後のテンポで演奏した際にもとの慣れたテンポに戻ろうと、無意識のうちに走ったり遅くなったりしてしまうのです。
そのようなことを避け、あらゆるテンポに柔軟に対応できるようにするには、先ほど説明した「インプット・アウトプット」という一連の作業をいろんなテンポの上で行うことです。
この時、テンポを必要以上に速くするのではなく、例えば・・・
- 80に慣れてきたから次は85で練習してみる
- 目標のテンポ120で叩けるようになったから今度は敢えて半分のテンポ60で叩いてみる
などのように、無理のない範囲でいろいろとテンポを変えて行うことも大切です。
曲練習の仕上げに、フレーズもしくは曲全体を通したものを録音したり人に聴いてもらったりするとより良いですね。
今まで気づかなかったリズムの癖の発見やテンポキープのチェックができますよ。
2.メトロノームに必要な機能とおすすめアプリ
メトロノームの種類
メトロノームの種類はゼンマイ式(振り子)式と電動式の2つに分けられます。
ゼンマイ式のクリック音は打楽器の音に埋もれてしまうので、振り子の動きを見て視覚的に合わせるといった用途に限定されてしまいます。
それに対し、電動式はスピーカーで音を出して合わせたりヘッドホンで聴いたりできるので使い勝手が良いです。
また、耐久性や持ち運びなどの面でも電動式のほうが優れています。
必要な機能
電動式メトロノームは実に多くの種類があり機能内容もテンポ変更だけのシンプルなものからボタンがたくさん付いているメカニックなものまで様々です。
機能は多いに越したことはないですが、所詮メトロノームは一定のテンポを刻む機械にすぎないので多機能でもほとんどが普段使用することがないでしょう。
私も「Dr.Beat」の最もハイスペックなモデルを7,8年ほど使っていますが、使っていない機能が8割ぐらいですね。
ただ、練習するうえで役に立つ機能もあります。
打楽器の練習において「最低限これはあったほうがいい」というメトロノーム機能は次の3つ
| タップ機能 | タップボタンを複数回押すことでそのテンポの速さを表示 |
|---|---|
| リズム機能 | 拍(ビート)を8分音符、16分音符、3連符に細分化 |
| ヘッドフォン(外部出力) | スピーカーやヘッドフォンへの出力。ドラム練習には必須。 |
メトロノームの選び方とおすすめアプリ
上記の3つの機能があるかどうかチェックして、あとはそれぞれの目的・用途に従って+αの機能を搭載したものを選ぶのが良いかと思います。
初めてメトロノームを選ぶ方はまず無料メトロノームアプリをダウンロードしてみるのが良いでしょう。
おすすめ無料メトロノームアプリ |
|
|
(Google play)
Google playには多くの無料メトロノームアプリがありますが、その中でも特におすすめはこの「ドラマーのメトロノーム」。 タップ機能や、8分音符、16分音符、3連符のボリューム調整などが直感的に操作でき、音を出さなくてもメトロノームの機能を果たす視覚効果も工夫が凝らされています。 また、自分のカスタマイズしたセッティングをリストとして保存できる機能は非常に便利。 扱いも簡単で5分もあれば慣れます。
|
(Apple store)
ラディックユーザーは要チェックの無料メトロノームアプリ。 テンポ変更がダイヤル式なので、スピーディーにテンポを変えられるところは◎ その他の機能は少なめ。 タップ機能が搭載されていること&「Ludwigロゴ」入りという2つに魅力を感じておすすめしました。 機能が少ない割には「Ludwigロゴ」を変えられるといったところも気に入りました。 練習のモチベーションを上げてくれることに期待して・・・ |
メトロノームアプリはちょっとした練習やテンポの確認など、緊急時の使用に便利です。
ただ、電話やメールなど他のアプリが起動したときに切れてしまったり、バッテリーを消耗して携帯本来の機能の妨げになるので、腰を据えて行う練習には向きません。
また、市販メトロノームは高価なものではないので持っていない方は用意しましょう。
おすすめ市販メトロノーム
やはりドラマーに定評のあるローランド社の「Dr.Beat(ドクター・ビート)」がおすすめです。
私が使っている古いモデルには[オート・パワー・オフ]という機能がないので、「電源を消し忘れて翌日使おうと思ったら電源が入らない・・・」といったことがしばしばありました。
今のモデルにはこの機能はしっかり搭載されています。
Dr.Beatは3つのラインナップがありますが、目的・用途に合わせて「DB-30」、「DB-90」のどちらかを選択すると良いです。
シンプル&コンパクトでとても使い勝手の良いメトロノームです。
最低限必要な機能である1.タップ機能、2.リズム機能、3.ヘッドフォン(外部出力)が搭載されているので、こだわって使わない限り、もの足りなさを感じることはないでしょう。
背面にクリップが付いているので、譜面台やポケットに引っ掛けることも可能です。
電池の交換にドライバーを使うのがやや難点ですが、60分操作しなかったら自動的に電源が切れる[オート・パワー・オフ機能]でしっかりカバーしています。
ドクター・ビートの最上位モデル。
まず、なにより操作性が良く、ボリュームもテンポも目標の値にスピーディーに変えられるところが良いです。
メトロノームの「ピッピッ」という甲高い電子音はずっと聴いてるとちょっと耳が疲れてくるとよく言われます。なので、「コッコッ」といったトラディショナルなサウンドや「ワン・ツー・スリー・フォー」というヒューマン・ボイスなど4種類のクリック音が選べるというところが意外に大事なポイントです。
その他の機能は、曲の音源を流しながら練習したい方に向けた『インプット端子』、ローランドV-Padと併用して使う『リズム・コーチ』、複雑なビートを組み合わせてオリジナル・パターンの作成ができる『ノート・ミキシング機能』などかゆいところに手が届く仕様になっています。
メトロノームの機能としてはDB-30で十分ですが、外部機器と連結してより質の高い練習を求める方はこちらの検証をおすすめします。