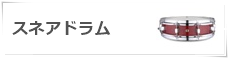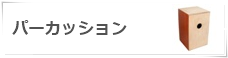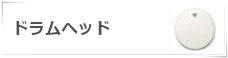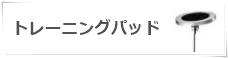スネアドラムのチューニング 〜良い音を創るため心得〜
“良い音”を創るために心得
“良い音”は1つではない
そもそも、あなたも他の人も好きな「万人が好む絶対的スネアサウンド」は存在しないのです。
う〜ん・・・このフレーズ、なんか面白いな。「万人が好む絶対的スネアサウンド!!」ぷぷっ^^
こんなスネアがあったら教えてくださいね〜(笑)

さて、次の問題は解けますか?
問.1)1+1=□
問.2)良い音=□
問1は簡単、答は1つ「2」ですよね。
それでは、問2はどうでしょうか?上記のテーマででてきた「心地よく感じたその音こそあなたにとっての“良い音”になるわけです」も1つの答だと思いますが、あなたにとっての答、あるいは他の人にとっての答・・・というように“良い音”に対しての答は答えた人の数の分だけ存在します。
つまり、数学の分野において答ははっきりと数字で表されますが、音楽など芸術の分野に共通していえることは、“良い音”の答は1つではないということです。(例えば絵画なんかもそうですが、新しく描いた絵をある人にはまったく評価されなくても違う人には評価され高値で買ってもらえたりって話ありますよね。)
“良い音(良い音楽)”は聴き手によって千差万別に存在する
ということです。
音楽と向き合う上でこの考え方はとても大事な要素です。一人よがりな音楽は自己満足に過ぎません。
多くの人を魅了するプレイヤーになるための根本的な考え方の1つとして頭の奥に残しておきましょう。
それでは次に、多くの聴き手を魅了する音(音楽)の見つけ方、創り方について解説していきます。
“良い音”の創り方
「インプット」、「アウトプット」を繰り返す
インプットについて
ここでいうインプットとは楽器の音を耳から聴いて脳に記憶するということです。
前のテーマで「絶対的な良い音はなく、良い音は聴き手によって千差万別に存在する」と結論づけましたが「多くの人が好む音」は存在しますよね。
音の他にも、「おいしい料理」、「美しい風景」、「いい匂い」など大多数の人が「いい!」と五感で感じるものにはいろんなものがあります。
このような「多くの人が好むもの」の定義をここで論理的に説明することはできませんが、その基準は知らず知らずのうちに出来上がっているものです。
それは名曲と言われるところにあったり、人気バンドのドラマーが奏でる音だったり・・・

その音を幅広く感じとり、それらを頭の中に記憶する。
これがここでいう「インプット」です。
ただし、良い音は1つではなく曲の雰囲気や音楽ジャンルごとに変わってきますよね。
そこが多くのプレイヤーを悩ませる音作り(チューニング)の難しいところでもあり、また醍醐味でもあります。
多くの人の心を魅了するプレイヤーはいろんな音楽からそれらを集めて良い音として蓄えています。
音の引き出しは多ければ多いほどいいですよね。
いろいろな曲をできるだけ生で聴いて、音楽ジャンルや曲の雰囲気に合う音を感じとる
ただなんとなく聴くよりも注目したい音にスポットをあてて意識的に聴くとより効果的にインプットできると思います。
アウトプットについて
アウトプットは拾い集めた情報(音)を自分で創り出すということです。
具体的には、理想の音にチューニングして実際に演奏するまでのことをいいますが、アウトプットのほうが労力的には大変な作業になります。
なぜならアウトプットには理想の音を表現するための技術も必要になってくるからです。

打楽器は叩けば音が出るもの。
他の楽器に比べれば簡単そうに見えますが、やはり理想の音を出すための技術は簡単には習得できません。
そもそも、一流プレイヤーが出す音とアマチュアの方が出す音の違いがわからないという方はまだまだインプットが足りないということになります。
私の知り合いのテノール歌手は以前、理想の声質にするため声帯の手術をしました。
手術前と手術後ではやや違うものの言われていないと自分には気づかないぐらいですが、彼の中では求める声質(音)に近づいたと満足しています。
歌手にとっては声が楽器ですからね、意識が高い彼は技術でカバーできない部分を追求した結果、選んだ手段なのでしょう。
スネアドラムの場合、インプットした理想の音に近づけるためには楽器の選び方、チューニングの仕方が大きく関わっています。(それ以外にも叩き方などの技術面やミキシングなどの音の加工の仕方などもありますが、それについてはこのサイト内で別途に掲載していきたいと思います)
なので・・・
理想の音を求めながら楽器の性質・形態やチューニングによる音の違いを研究する
ことで、インプットした情報をより定着させプレイヤーとしての表現力(アウトプット力)がアップするのです。
≪まとめ≫
「人はインプットとアウトプットの連続である」と言われていますが、音楽もまさにその通りだと思います。
ここで説明したインプットとアウトプットを繰り返すことで、今回のテーマである“良い音”をあらゆる場面において表現できるプレイヤーへと成長できるのです。

私も、音大受験のころは打楽器(特にスネアドラム)と1日に7、8時間向き合っていました・・・
今思えば、アウトプット作業に偏っていたと反省するところもありますが、その時期はとにかく技術習得に時間を費やしていましたね。
テクニックの習得以外にもスネアドラムであればシェル、ヘッド、スナッピーなどの材質による音の違いを徹底検証など。
必死になってもがいていたあの頃に戻りたいとは思いませんが・・・そのときに得たものは今の音楽活動する上で非常に役立ってます。
初めはのうちは真似でも構いません。好きなアーティストのスネアモデル、その人が使用しているドラムヘッド、スナッピーなどの情報を調べて、それと同じようなサウンドに限りなく近づけるためにチューニング(音作り)したり研究することが、最終的に自他共に認める“良い音”を創っていく上で役立つに違いありませんから!
初心者の方はスネアドラムのパーツを具体的にどう変えたり調整したらどのように音が変わるか、わからないかもしれません。
良い音作りをするにはまず楽器を知ることから始まります。
スネアドラムの基本構造を知るではスネアドラムの各パーツ名称とその役割について解説していますので、参照にしていただければと思います。
それでは、次に「楽器本来の“鳴り”を活かすスネアドラムのチューニングの仕方」をテーマに、実際のチューニングの手順を各ポイントをおさえながら解説していこうと思います。
>>楽器本来の“鳴り”を活かすスネアドラムのチューニングの仕方
関連するページ