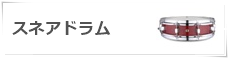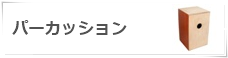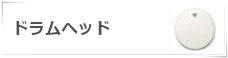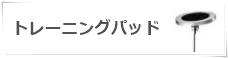スネアドラムのパーツ名称とその役割
代表的な打楽器スネアドラムの基本的な構造をしっかり把握してより良い音作り(チューニング)に活かしましょう!

ストレイナー

裏側のヘッドにスナッピーを接触(ON)させたり解除(OFF)したりする装置のことで、備え付けられた回転つまみでスナッピーの張り具合も調整できます。
メーカーによって形状の種類は様々です。
ヘッド
ヘッドは表面と裏面に張られますが、その素材や厚みなどの違いによっていろんな種類があり、各製造メーカーは様々なラインナップを揃えています。(詳しくはこちらを参照)
もともとは本皮(主に牛の皮)が使用されていましたが、今はプラスティック製が主流です。
現在でもプロ・オーケストラの方はこだわって本皮を使う人が多いですね。
フープ
シェル(胴)にヘッドを固定するためのものです。
主な種類としてプレスフープ、ダイカストフープ、フランジフープ、ウッドフープがあり、それぞれシェルとの相性の良し悪しがあることも頭に入れておくことが大事です。
ラグ
フープの穴に通したテンション・ボルトを差し込んむパーツです。
シェルとの接点が少ないほど(響きを妨げないので)良く鳴るオープンなサウンドになります。
空気穴
叩いたときにヘッドやシェルの響きを逃がす役割がありベント・ホールとも呼ばれます。
試しにこの穴を塞いで叩くとやや音が詰まるのがわかるかと思います。
テンション・ボルト
チューニング・ボルトとも呼ばれ、ラグへの差し込み具合いでヘッドの張力を調整します。
ラグやフープにも共通して言えることですが、スネアのモデルのによってその数も違います(6本〜10本)。
スナッピー

裏側のヘッド接触させることで「ジャッ」という歯切れの良い音が加えるスネアドラムの最大の特徴でもあるパーツです。
スネアのサウンド大きく左右するスナッピーは素材、本数などによって種類も豊富です。(詳しくはこちらを参照)