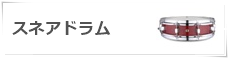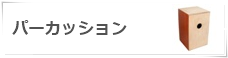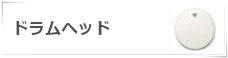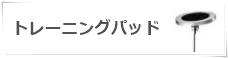音楽ジャンル別にみる打楽器の役割
世界にはさまざまな音楽ジャンルが存在します。
その中でも我々日本人に馴染みあるのはポップス、ロック、ジャズ、演歌などの「ポピュラー音楽」でしょう。
そして、そのポピュラー音楽の根源的存在である「西洋音楽(クラシック音楽)」。
音楽は時代の流れとともに形を変えながら、その楽器の形や使い方も変化しています。
例えば、クラシック音楽においては、シンバル、大太鼓(バスドラム)、小太鼓(スネアドラム)の演奏者は一人ずつ割り当てられますが、ポピュラー音楽においてはそれらの楽器をまとめた「ドラムセット」という一つの楽器として扱われ、演奏方法も異なります。
また、異なるのは演奏方法だけではありません。
打楽器が曲の中でどのような役目を担い、どのような効果をもたらしているのかを考えたとき、「ポピュラー音楽」と「クラシック音楽」ではこれまた大きく異なる部分があるわけです。
ここでは、この2つの音楽ジャンルを比べたときに気づかされる相違点について、「打楽器の役割」という観点から説明したいと思います。
音楽における打楽器の役割記事一覧
打楽器の役割 〜ポピュラー音楽〜
皆さんご存知の通り、ポピュラー音楽の中で「ドラムセット」は欠かせない存在です。(バンドや曲によってはドラム以外の様々な打楽器を扱うパーカッショニストが編成に加わっている場合も少なくありませんね。)リズムの要一般的にポピュラー音楽の世界では“リズム・セクション”と言えば、まずビートを作りだすドラマーと...
打楽器の役割 〜クラシック音楽〜
ポピュラー音楽における打楽器(特にドラムセット)の役割は、「一定のテンポのもとで刻まれるリズムの要」であると説明していますが、クラシック音楽の場合、それとは大きく異なります。時間とテンポクラシック音楽にはテンポ60といった数字で表記されず、「Andante(アンダンテ)※歩くような速さで」や「All...