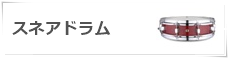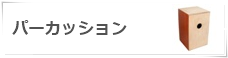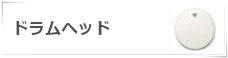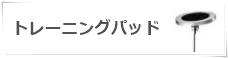構え方、手の動きについて | マリンバ講座 第4回
前回マレットの持ち方について説明しましたが、今回はマリンバを演奏する際の構え方、手の動きについて解説したいと思います。
構え方について
マレットをもってマリンバを演奏するときのフォームを確認していきましょう。
手をまっすぐに伸ばして(写真1)、手首が自然に曲がる位置(手の甲が上の状態)を確認した後、肘をひきます(写真2)。
 |
 |
| 写真1 | 写真2 |
肘の角度
肘を曲げるときは、わきが広がりすぎたりしないようにしましょう(写真3)。
わきを広げすぎると、肩に力が入りやすくなるうえ、マレットをあげたときに外側にそれて間違った軌道をつくってしまいます。
逆に、わきを身体にくっつけてもいけません。こちらも委縮して力が入ってしまいます。
| ○ | × |
 |
 |
| 写真3 | 写真4 |
マレットの角度
マレットが手の延長上にありますか?
手の甲に対してあまり横すぎると手首を動かしにくくなるので注意しましょう。
| ○ | × |
 |
 |
| 写真5 | 写真6 |
手の動きについて
手の軌道を確認しながらゆっくり動かしてみましょう。
上にあげるとき、さげるとき、同じ軌道上を通ります。
あげるとき、わきがひらいて外側にそれないように注意!そうなると斜めから鍵盤をたたくことになりますから腕の重さがしっかりかからなくなります。
あげるときは手首が先にそりかえらないように、マレットの先で半円を描くように。
上にあげてからも手首がそりかえってマレットが下にたれさがらないようにしましょう。
肘を支点に動かしてみるのもいいでしょう。
腕、ひじ、手首それぞれの段階があることがわかります。例えば手首だけを使っているように見える早い動きでもかならず、腕や肘が連動しています。途中で流れを遮断してはいけません。波の動きや、ロープなどを地べたにおいてムチのように動かした動きを想像してみて下さい。
そして、手をおろすときは腕(もしくは身体)から水が流れ出て肘を通り、手首を通過し放出されるようなイメージをしてみて下さい。
次回、腕、肘、手首それぞれの動きを確認しながら音を鳴らしてみます!
上から
 |
 |
 |
横から
 |
 |
 |
腕の重さを感じる
他の打楽器と同様、マリンバ演奏に“脱力”は欠かせません。
ここでいう“脱力”というのは、力まかせに叩くのではなく、重力(腕やマレットの重み)を最大限に利用するということです。
マリンバの演奏は、基本的には「手を上にあげてから下におろす」動作ですが、このときの手全体の動きや自らの腕の重さを、“脱力”のもとで確認したいと思います。
電車やバスでつり革につかまるとき、身体をつり革に預けている感覚があると思います。
その感覚のまま、ふと放した時、手は腕(ひじ)の方からだらんと落ちると思います。
そのような感覚を自分で感じてみて下さい。そしてそれを何度か繰り返しでみましょう。
どうでしょう、上から下に手が重力によって勝手に落ちる感覚を感じとれますか?
はじめはよくわからないかもしれませんが、あまり考えすぎないでやってみて下さい。
〜まとめ〜
フォームを確認していきましたが、もちろん曲を演奏したり、マリンバは大きい楽器ですし、常にこのような角度でやれない場合もあるでしょう。
しかし、芯のある音を出すための一番いいポディデョンはあるはずです。
それをどうもっていくかは身体の重心の移動などが関わってきます。(ここでの詳しい説明はしません)
要するに身体の自然な動きにマレットの先まで伴っていればいいのです。
人それぞれに自分のやりやすい自然なやり方がありますし、それを自然というかもしれません。
しかし何かやりづらい、早い動きができない、いい音が出ないなどと問題が生じたときに、無理な力を入れている角度に手がなっていたり、身体の位置が悪かったりすることがあるかもしれません。
こういった動きを考えるのに少し身体の動きのメカニズムを知っておくといいと思います。お子様には少し難しいですが、ある程度成長すると、体で覚えるではなく頭で知ることを重要視していかなければなりません!少しピンとこないかもしれませんが、このことはいろんな面で役に立ちますよ!
身体の動きを理解しておけば、身体にとって一番自然な動きがわかります。(身体に負担や痛みが出で来ないことにつながります)楽器をずっと長く続けていくには、大切なことです。
ここで時間をかけることは、いい音を出すこと、手が速く動くようになることなど技術面でとてもいい効果を出すことになります!
マリンバレッスンや体験レッスンの詳細はこちらでご案内しています。
どうぞ、お気軽にご覧ください♪
マリンバ講座メニュー一覧