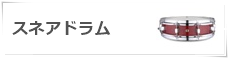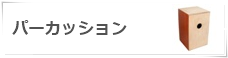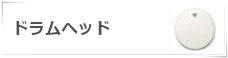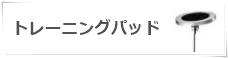‘إٹyٹي‰‰‘t‚ة‚¨‚¯‚éپg’E—حپh‚جڈd—vگ«‚ًچl‚¦‚é
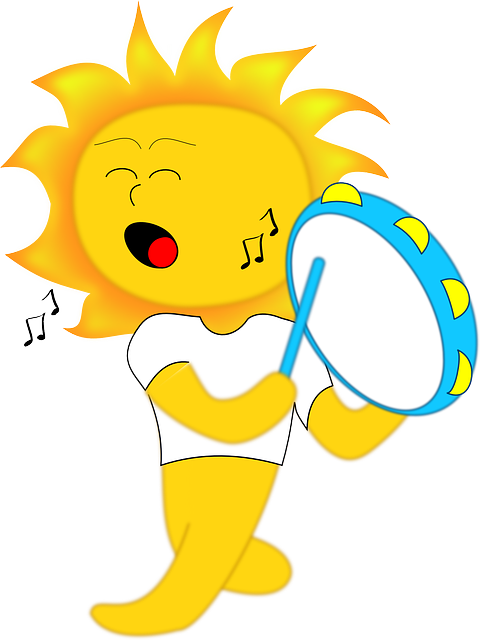
ƒXƒ|پ[ƒc‚ج•ھ–ى‚ةŒہ‚炸پA‰¹ٹyپi‘إٹyٹيپj‚ج•ھ–ى‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à‰¹‘ه‚âƒhƒ‰ƒ€ƒŒƒbƒXƒ“‚ب‚ا‚ج‘½‚‚ج‹³ˆçŒ»ڈê‚إژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚éپg’E—حپh‚ئ‚¢‚¤چl‚¦•ûپB
‚ب‚؛پA‚±‚±‚ـ‚إ’E—ح‚ھ‚±‚±‚ـ‚إڈd—vژ‹‚³‚ê‚é‚ج‚©پH
‚ـ‚½پA’E—حپi—ح‚ً”²‚‹Zڈpپj‚ًڈK“¾‚·‚邱‚ئ‚ح‰‰‘t‚ة‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‰e‹؟پEƒپƒٹƒbƒg‚ھ‚ ‚é‚ج‚©پH
‚±‚±‚إ‚حپA‘إٹyٹي‰‰‘t‚ة‚¨‚¯‚éپg’E—حپh‚جڈd—vگ«پE‰e‹؟—ح‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚ؤ‚ف‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
’E—ح‚ئ‚حپH
ˆê”ت“I‚ةپg’E—حپh‚ئŒ¾‚¤‚ئپu‘ج‚©‚ç—ح‚¾”²‚¯‚ؤ‚®‚ء‚½‚è‚·‚éپB‚ـ‚½پAˆس—~پE‹C—ح‚ھگٹ‚¦‚邱‚ئپBپv‚ًˆس–،‚µ‚ـ‚·پB
‹ظ’£‚µ‚ؤ‚¢‚éڈê–ت‚âپAگV‚µ‚¢•¨ژ–‚ًژn‚ك‚ؤڈ‚µƒ€ƒL‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚éژپA‚»‚جژü‚è‚جگl‚ةپuŒ¨‚ج—ح‚ً”²‚¢‚ؤٹy‚ةپEپEپEپv‚ب‚ا‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚±‚جڈêچ‡‚ج’E—ح‚حپuگ¸گ_“I‚ب‹ظ’£‚ً‚ظ‚®‚µ‚ؤ‹C‚ًٹy‚ة‚·‚éپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µپA‚±‚±‚إ‚¢‚¤پg’E—حپh‚ئ‚حپuƒXƒeƒBƒbƒN‚ًƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚·‚邽‚ك‚ج•K—vچإ’لŒہ‚ج‹ط“÷‚ًژg‚¤‚ھپA‚»‚êˆبٹO‚ج—]Œv‚ب—ح‚ً”²‚پv‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚·پB
‚ ‚‚ـ‚إ‚àپAپu‹C—ح‚ً”²‚پv‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپ¨„،„§پL„t`„¥„¢ہقظپ`
گ¸گ_“I‚ب‹ظ’£‚ً‚ظ‚®‚·ڈêچ‡پAگ[Œؤ‹z‚µ‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚إپA‚·پ`‚ء‚ئ—ژ‚؟’…‚«‚ًژو‚è–ك‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µپA‘إٹyٹي‚ة‚¨‚¯‚é’E—ح‚حŒ¾‚¢ٹ·‚¦‚ê‚خپu—ح‚ً”²‚‹Zڈpپv‚ج‚±‚ئ‚إپAˆêŒ©ٹب’P‚»‚¤‚ة•·‚±‚¦‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ê‚ھˆسٹO‚ئ“‚¢‚ج‚إ‚·پB
’E—ح–@‚ً–W‚°‚éٹشˆل‚ء‚½‘t–@پE—ûڈK
- ”²‚¯‚ج—ا‚¢‰¹‚ًڈo‚µ‚½‚¢پI
- •\Œ»‚ج•‚ًچL‚°‚邽‚ك‚ةژè‚ً‘پ‚“®‚©‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚肽‚¢پI
- ’·ژٹشƒvƒŒƒC‚µ‚ؤ‚à”و‚ê‚ة‚‚¢‘t–@‚ًڈK“¾‚µ‚½‚¢پI
ƒhƒ‰ƒ€‚â‚»‚ج‘إٹyٹي‘S”ت‚ً‰‰‘t‚·‚éڈم‚إپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب—~‹پ‚حŒüڈمگS‚ج‚ ‚éƒvƒŒƒCƒ„پ[‚إ‚ ‚ê‚خ’N‚à‚ھژv‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚و‚ثپB
‚µ‚©‚µپAژں‚ج‚و‚¤‚بٹشˆل‚ء‚½‘t–@‚â—ûڈK‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚حŒّ‰ت‚ھ‚ب‚¢‚ا‚±‚ë‚©پA‚©‚¦‚ء‚ؤ‹tŒّ‰ت‚ة‚ب‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚ج‚إپAڈ\•ھ‚ة’چˆس‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢‚إ‚·پB
- ”²‚¯‚ج—ا‚¢‘ه‚«‚ب‰¹‚ً–آ‚ç‚·‚½‚ك‚ة—ح”C‚¹‚ة’@‚پB
- ‘¬‚ژè‚ً“®‚©‚·‚½‚ك‚ةپAƒXƒeƒBƒbƒN‚ً‚¬‚مپ`‚ء‚ئˆ¬‚èپAکr‘S‘ج‚ج‹ط“÷‚ًگk‚ي‚¹‚ب‚ھ‚çکA‘إ‚·‚éپB
- ’·ژٹشƒvƒŒƒC‚µ‚ؤ‚à”و‚ê‚ة‚‚¢‹ط“÷‚ًچى‚邽‚ك‚ة‚ب‚ٌ‚ç‚©‚ج‹طƒgƒŒ‚ًچs‚¤پB
‚à‚؟‚ë‚ٌƒXƒeƒBƒbƒN‚ًژ‚ء‚ؤٹyٹي‚ً’@‚ˆبڈمپA‹ط“÷‚ح•K—v‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·‚ھپA–`“ھ‚إ‚àŒ¾‚ء‚½‚و‚¤‚ة•K—vˆبڈم‚ة—]Œv‚ب‹ط“÷‚ًژg‚¤‚±‚ئ‚حپA‰¹ٹy•\Œ»‚ج–W‚°‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
“ء‚ةڈ‰گSژز‚ج•û‚ة‘½‚¢‚ج‚ح2”ش–ع‚جپu‹ط“÷‚ًگk‚ي‚¹‚ب‚ھ‚çکA‘إ‚·‚éپBپv‚إ‚·پB
ƒXƒeƒBƒbƒN‚ً‹‚ˆ¬‚肵‚كپAŒ¨‚©‚çژwگو‚ـ‚إ‚جکr‘S‘ج‚ًچd’¼‚³‚¹‚ب‚ھ‚çکA‘إ‚·‚邱‚ئ‚حٹm‚©‚ةپAƒXƒeƒBƒbƒN‚ًˆ¬‚ء‚½‚خ‚©‚è‚جگl‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ح‚»‚ê‚ھژè‚ًچإ‚à‘¬‚“®‚©‚·ژè’i‚ب‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
‚½‚¾‚µپAٹç‚ًگ^‚ءگش‚ة‚µ‚ب‚ھ‚ç’@‚‚»‚ج‚و‚¤‚ب’@‚«•û‚حپA’E—ح‚µ‚½’@‚«•û‚ة”ن‚ׂé‚ئپA‘¬“x‚ج–ت‚¾‚¯‚إ‚ب‚ژ‘±گ«‚ة‚à—ٍ‚è‚ـ‚·پB
‚ـ‚½پA‘إ‰¹‚ح‰¹گFپE‹‚³‚ب‚ا‚ً‰¹ٹyƒVپ[ƒ“‰‚¶‚ؤ‘½چت‚ة•د‰»‚³‚¹‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
—ح”C‚¹‚ة’@‚‰¹‚ح‘@چׂ³‚ةŒ‡‚¯‚½’P’²‚ب‰¹‚ة‚ب‚è‚ھ‚؟‚ب‚ج‚إ‰¹ٹy•\Œ»‚ج•‚ح‹·‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إ‚·پB
’E—ح‚ًگg‚ة•t‚¯‚é2‚آ‚جƒپƒٹƒbƒg
‚±‚±‚إ‚حپAŒّ—¦“IپEچ‡—“I‚ب’E—ح‘t–@‚ًگg‚ة•t‚¯‚邱‚ئ‚إگ¶‚ـ‚ê‚é2‚آ‚جƒپƒٹƒbƒg‚ً‰ًگà‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
‘إٹyٹي‚جژي—ق‚ح‘½ژي‘½—l‚ة‘¶چف‚µپAٹyٹي‚ة‚و‚ء‚ؤ’@‚«•û‚âƒoƒ`پiƒXƒeƒBƒbƒNپAƒ}ƒŒƒbƒg‚ب‚اپj‚ھˆظ‚ب‚è‚ـ‚·پB
ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹‚ج‚و‚¤‚بڈ¬‚³‚¢ٹyٹي‚ة‚حˆê”ت“I‚ة‚حƒrپ[ƒ^پ[‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‹à‘®‚ج–_‚ھ—p‚¢‚ç‚êپA“؛ètپiƒ^ƒ€ƒ^ƒ€پj‚ة‚ح‘ه‚«‚ڈd‚¢گê—p‚جƒoƒ`‚ھ—p‚¢‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ةپA‚»‚ꂼ‚ê‚جٹyٹي‚ج‘ه‚«‚³پA‘fچقپA‚ـ‚½‚ح‰¹ٹyڈê–ت‚ة‰‚¶‚ؤچإ‚àپg—ا‚¢‰¹پh‚ھˆّ‚«ڈo‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚ ‚ç‚©‚¶‚كچl‚¦‚ç‚ꂽƒoƒ`‚ھ—pˆس‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ثپB
–{—ˆ‚حƒoƒ`‚ھژ‚آڈd‚³‚ئڈd—ح‚ً—ک—p‚·‚邾‚¯‚إڈ\•ھ‚بٹyٹي‚ج–آ‚è‚ًڈo‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«پA‚»‚جƒoƒ`‚ة—^‚¦‚éپgڈd‚فپh‚ئپg‘¬‚³پh‚ً’²گك‚µ‚ؤ‰¹گF‚â‹ژم‚ً•t‚¯‚é‚ج‚ھ‘جپiکr‚âژèپj‚ج–ًٹ„‚إ‚·پB
—v‚·‚é‚ةپAٹyٹي‚ئ‚»‚جٹyٹي‚ً–آ‚ç‚·ƒoƒ`‚جƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ھ—ا‚¢ڈَ‘ش‚إ•غ‚½‚ê‚ؤ‚¢‚ê‚خپA‚»‚±‚ة‰ء‚ي‚éٹO•”‚©‚ç‚ج—]Œv‚بˆ³—ح‚ح•K—v‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
‚ـ‚½پAگU‚è‰؛‚낵‚½ƒXƒeƒBƒbƒN‚ھ‘إ–ت‚ًƒqƒbƒg‚·‚éڈuٹش‚حƒXƒeƒBƒbƒN‚ًˆ¬‚è’÷‚ك‚¸ٹJ•ْ‚³‚¹‚ؤ‚¨‚‚±‚ئ‚إپAƒwƒbƒh‚جگU“®‚ً—}‚¦‚邱‚ئ‚ب‚ٹyٹي‚ھژ‚آژ©‘R‚ب‹؟‚«‚ھ“¾‚ç‚ê‚é‚ج‚إ‚·پB
ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{پ[ƒ‹‚ً‘جˆçٹظ‚ة’e‚ـ‚¹‚鉹‚ء‚ؤ•·‚¢‚ؤ‚ؤگS’n‚¢‚¢‚إ‚·‚و‚ثپB
ƒCƒپپ[ƒW‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚±‚ê‚ة‹ك‚پAƒoƒXƒPƒbƒgƒ{پ[ƒ‹‚ھ’n–ت‚ةƒqƒbƒg‚·‚éڈuٹش‚حژè‚©‚çٹ®‘S‚ةٹJ•ْ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB
‰¼‚ةپA’n–ت‚ةƒqƒbƒg‚·‚éڈuٹش‚àژè‚©‚ç—£‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خگU“®‚ح—}‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ج‚ئ‚«‚ا‚ٌ‚ب‰¹‚ھ‚·‚é‚©‚ح‘z‘œ‚إ‚«‚é‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
‰¹گF‚ًچى‚é—v‘f‚حپAٹyٹي‚ج‘ه‚«‚³پA‘fچقپAŒ`‚ب‚ا‚ةˆل‚¢‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚’@‚«•û‚جˆل‚¢‚ة‚و‚ء‚ؤ‚à•د‰»‚µ‚ـ‚·پB
ڈ¬‚³‚ب‰¹پAگ[‚¢‰¹پA‰s‚¢‰¹پA–¾‚é‚¢‰¹پAŒy‚¢‰¹‚ب‚اپA‚¢‚ë‚ٌ‚بƒTƒEƒ“ƒhƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^پ[‚ًˆّ‚«ڈo‚·‚½‚ك‚ة‚حƒXƒeƒBƒbƒN“™‚ًگU‚è‰؛‚ë‚·پg‹——£پhپAپg‘¬‚³پhپAپgڈd‚³پh‚ً‘½—l‚ة•د‰»‚³‚¹‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
—ل‚¦‚خپAƒXƒlƒAƒhƒ‰ƒ€‚إپuڈ¬‚³‚¢‰¹پvپu‰s‚¢‰¹پvپuŒy‚¢‰¹پv‚ً•\Œ»‚µ‚½‚¢ڈêچ‡پAژں‚ج‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB
ڈ¬‚³‚¢‰¹پEپEپEپEپEگU‚è‰؛‚ë‚·‹——£‚ً’Z‚‚·‚é
‰s‚¢‰¹پEپEپEپEپEگU‰؛‚낵پAگU‚èڈم‚°‚جƒXƒeƒBƒbƒN‚ة‘¬‚³‚ً‰ء‚¦‚é
Œy‚¢‰¹پEپEپEپEپEƒXƒeƒBƒbƒN‚ھ‘إ–ت‚ة‚ ‚½‚éڈuٹش‚ة‰ء‚ي‚éڈd‚ف‚ًŒyŒ¸‚³‚¹‚é
‚±‚ج‚و‚¤‚ةپAƒXƒeƒBƒbƒN‚ھڈd—ح‚إژ©‘R‚ة—ژ‰؛‚·‚éƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ًٹî–{‚ةپA‚ب‚ٌ‚ç‚©‚ج—v‘f‚ً‰ء‚¦‚邱‚ئ‚إ‰¹‚ة•\ڈî‚ً‚آ‚¯‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB
‚³‚ؤپAگU‚è‰؛‚ë‚·‹——£‚ًƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚·‚é‚ج‚ح”نٹr“I—eˆص‚إ‚·‚ھپA—ژ‰؛‚·‚éƒXƒeƒBƒbƒN‚ة‘¬‚³‚ً‰ء‚¦‚½‚èڈd‚ف‚ً‰ء‚¦‚½‚è‚·‚é‚ج‚ة‚ح‚؟‚ه‚ء‚ئ‚µ‚½ƒRƒc‚ھ•K—v‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB
‚»‚ê‚حپAکr‚©‚çژèگو‚ة‚©‚¯‚ؤ‘¶چف‚·‚é4پ`6‚جٹضگك‚ًچ‡—“IپEŒّ‰ت“I‚ة“®چى‚³‚¹‚邱‚ئ‚إ‚·پB
‚»‚µ‚ؤپAٹضگك‚ًڈ_“î‚ة‰ز“®‚³‚¹‚邽‚ك‚ة‚ح’E—ح‚ھ•K—v•s‰آŒ‡‚ة‚ب‚é‚ي‚¯‚إ‚·پB
’E—ح‚ج‚à‚ئٹضگك‚ًڈمژè‚—ک—p‚·‚邱‚ئ‚إپA‘½چت‚ب‰¹گF‚ً–³—‚ب‚ڈ_“î‚ةˆّ‚«ڈo‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ج‚إ‚·پB
ڈع‚µ‚‰ًگà‚·‚é‚ئ‚؟‚ه‚ء‚ئ’·‚‚ب‚é‚ج‚إپA‰¹گF‚ة‘خ‰‚³‚¹‚éٹضگك‚ج‹ï‘ج“I‚ب—ک—p•û–@‚ح‚ـ‚½•ت‚ج‹@‰ïپi‹ك“ْ’†پj‚ة‚¨کb‚µ‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
ٹî‘b—ûڈKƒپƒjƒ…پ[ˆê——
ڈ‰‹‰•ز